昨日、城見公民館で郷土史本の打合会議があり、
本の添付物として散策マップに必要な写真を撮りに茂平に来た。
ヒルタ工業の工場付近、「小迫新開跡地」。

小迫新開では戦後の一時、塩田だった。
高丸城跡。

白砂青松であった「苫無」海岸付近。
| 2016年9月1日 木曜日 9:49〜12:49 | ||
| 笠岡市茂平(もびら) | ||
昨日、城見公民館で郷土史本の打合会議があり、
本の添付物として散策マップに必要な写真を撮りに茂平に来た。
ヒルタ工業の工場付近、「小迫新開跡地」。

小迫新開では戦後の一時、塩田だった。
高丸城跡。

白砂青松であった「苫無」海岸付近。

![]()
阿浜は通称「さらやま」と呼ばれていた。皿を作っていた。
「吉備焼」。

明治末に焼き物を始めた。
窯元の水川さんが明治・大正・昭和の跡を案内してくれた。

これは土をふるいにかける場所。

吉備焼が茂平で始めた理由の一つに粘土があったこと。
その粘土を写真左の円形の井戸で最初にふるいにかけ、右の井戸で二度目のふるい、それを右の苗代に似た場所で練って焼き物の土にするそうだ。

「登り窯」(のぼりがま)
明治40年頃から昭和40年まで使っていた。

「重油窯」と「石炭窯」。

昭和40年頃の吉備焼の海岸風景。

波返しは、役にたつ期間は短かった。
かつては窯の前まで砂浜がつづき、商品は砂浜から船で出荷していた。
波返しが出来、数年で海はなくなった。
![]()
元・茂平港。

龍王さまに行く。

これが瀬戸内海地方には数えきれないほどある「龍王」のうち、
非常に珍しい海の「龍王」。

茂平の「龍王さま」(りおうさま)は潮が満ちたら海底にあった。
珍しいといえば「社稷」の碑。

中国では国家を意味する社稷(しゃしょく)が茂平にある。碑は日本各地にある「地神」と同類。
現在編集中の「城見の歩み」によると、
笠岡市茂平3基、用之江1基、有田1基。福山市大門町5基、加茂町1基。
そのすべてが同時期で大正時代のもの、
「とんまん土手」または「とんま」。


現在は土手の中央を県道井原福山港線が横断する。
↑写真石垣まで波が打ち寄せていた。
![]()
![]() つぎ・茂平史跡巡り②
つぎ・茂平史跡巡り②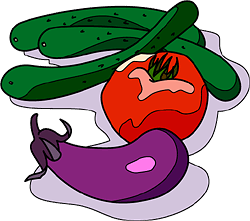 ③
③
2016年9月3日