| 2023年4月16日 日曜日 | 八日市 | 高山(こうやま) | 大江 | |||||
| 岡山県高梁市川上町高山&井原市芳井町東三原 ”高山市” | 8:20頃 | 9:15〜11:01 | 12:40頃 | |||||
![]()
弥高山に来たなら、必ず
「高山市」と「穴門山神社」の両方、または片方を訪れる。
今日は高山市(こうやまいち)を訪れる。
![]()
高山市は、
後月郡と川上郡に属し、
広島県東城や岡山県新見、瀬戸内海の笠岡を繋いだ物資の中継点として栄えた町。

今は残念ながら、限界集落の様相をみせている。
「岡山県史・自然風土」 岡山県 山陽新聞社 昭和58年発行
高山市
高山市には毎月己の日には市が立ち、
特に春秋二度ずつの市は大にぎわいだった。
牛市・魚市・藍市・煙草市が立ち、
新見あたりでも「魚がほしけりゃ高山へ行け」と言われていたという。
成羽川と小田川の分水嶺にあり、
もとの高山市と三原村の村境が入り乱れ、旧市場敷地権のあとを残している。

備中町史
高山市の市場圏は10里四方といわれ、井原・笠岡からも送られてきた。
輸送機関は馬背・牛背であり、近距離では人肩で物資が運び込まれた。
東城からは、米・木炭・麦・大豆・小豆・こんにゃく・菜種等が高山市を経由して笠岡へ、
またその逆に笠岡から(七日市・井原)〜高山市を経て
塩・魚類・海藻類の水産物、呉服等の日用品、砂糖、味噌等の調味料がもたらされた。

「岡山県史・自然風土」 岡山県 山陽新聞社 昭和58年発行
もともとこの地方の交通路は、
吉備高原の尾根筋を縦横にはしり、なかでも「東城馬」という言葉が示すように、
この高山市を通る道筋は、高原の幹線道であった。
笠岡へ八里、東城へ九里の道程で、
東城の米、
笠岡の海産物を運ぶ東城馬の中継地として発達していった。
東城〜河内〜油木〜上豊松〜花済〜杖立〜高山市〜千峰坂〜吉井〜井原〜七日市〜岩倉〜蛸村〜東大戸のコースを通り、
ここから小平井〜追分〜笠岡へ出るものと、
東大戸から西浜(ようすな)笠岡へ出るものがあり、駄送には二日を要した。
井原市。

高梁市。

道の真ん中に仔犬か猫か、そんなのが二匹じゃれあっていた。
写真に撮って拡大したらイタチだった。↓
JAの場所は高梁市。

「岡山県史・自然風土」 岡山県 山陽新聞社 昭和58年発行
高山市の市場圏については「高山八八里」と言われ、
八里離れた八方の地点、すなわち
東城・上下・高梁・成羽・笠岡・矢掛・福山・府中と結びついていたという。
郵便局の場所は井原市。


「美星町史」 美星町 昭和51年発行
後月郡東三原村枝郷高山上市は
古くから毎月5日、15日、25日の三度と2月10日の巳の日に市を立ててきたので、諸商人が近国近辺より商品を持って売買市が立っていた。
文政2年(1819)ごろには、
隣村の川上郡高山市村が新市場として繁盛するようになり、穀物、古着、小間物商が出入りを始めた。
穴門山神社の参道入口。
穴門山神社の門前町でもあった高山市の町は、この付近は完全に高梁市・井原市が不明。


備中町史
東城-高山往来
東城・高山往来は笠岡からの魚の運搬路として発展したものと考えてよい。
笠岡から高山市まで約8里、高山市から東條間約9里、高山市から新見約10里であり、高山市を中継点として発展していった。
現在もこの地方の商人は祭礼や正月、春のさわらは、笠岡の西浜まで買いに行くことが多い。
高山市は穴門山神社の門前町として栄え、また備中国における陸路輸送の中心地であり、馬継場として繁栄した。

![]()
![]() 大賀デッケン〜沢柳の滝
大賀デッケン〜沢柳の滝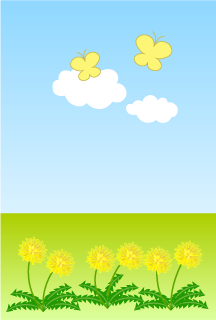
2023年4月18日