
 |
2022年7月13日 水曜日 埼玉県川越市幸町 川越商家・重伝建地区 | |||||||||||||
| 飯田橋 | 川越 | 千住 | 深川 | 東京駅 | 笠岡駅 | |||||||||
| 6:04発 | 7:26〜9:24 | 11:28〜12:10 | 12:44〜13:40 | 14:51 | 19:25着 | |||||||||

川越
蔵造りの町並み
「ブラタモリ」 NHK 角川書店 2016年発行
川越を象徴する蔵造りの町並みは、一番街エリア、
仲町交差点から札の辻までの約400mにわたって続きます。
道幅は元禄年間の頃のまま、「蔵造り」と総称される土蔵造りや塗家造り、
町家造りの商家に加え、近代洋風建築も散見できる。
国選定の「重要伝統的建築物群保存地区」です。




”小江戸”という言葉がぴったりで、”小京都”ではない。

外壁は黒漆喰、高く積んだ棟瓦、両開きの塗り戸。
重厚感たっぷり。


「時の鐘」。

「ブラタモリ」 NHK 角川書店 2016年発行
「時の鐘」
徳川家光の時代、川越城主・酒井忠勝が創建したといわれています。
城下に時を知らせるとともに、火の見櫓としても機能。
現在の時の櫓は4代目。
明治26年に起きた川越大火の直後に再建されたものです。
川越に蔵造りの町並みができたのも、この川越大火がきっかけでした。
類焼を免れたうちの1軒が、寛政4(1792)年に建てられた土蔵造りの店舗兼住宅(大沢家住宅=重文)。
これに倣い、東京から大工や左官などの江戸職人を呼んで造ったのが、現在も立ち並ぶ店蔵というわけ。
大沢家住宅前。

「川越まつり会館」や「大沢家」を過ぎると「札の辻」交差点があり、そこで重伝建地区は終了する。
札の辻。

公益社団法人 小江戸川越観光協会
いちばんがい
一番街
(蔵造りの町並み)
かつて、幕府が決めた法度や掟書きなどを町人に知らせるため、
高札(木の板)を高く掲げる場所であった“高札場(こうさつば)”が、一番街北端の「札の辻」にありました。
一番街は「札の辻」からみて南に位置するため「南町」とされており、江戸時代後期に川越城下の商業の中心地として栄えました。
現在も国指定重要文化財である大沢家住宅などの建築文化財が数多く残っています。
明治26年3月17日に発生した「川越大火」により街の3分の1が焼失してしまいましたが、
この際に蔵造りの建物だけは焼け残り、防火建築という観点から、一番街には蔵造り商家の建築が進みました。
江戸の面影をとどめる蔵造りの町は、平成4年に電柱・電線の地中埋設工事が完了し、
平成11年に「重要伝統的建造物群保存地区」に選定され、現在は多くの観光客でにぎわう川越の象徴的な存在となっています。
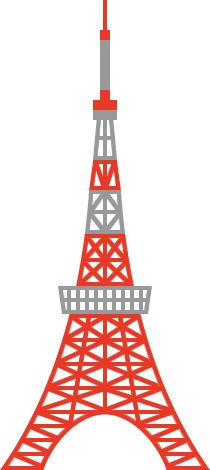
![]()
![]() 川越城本丸御殿
川越城本丸御殿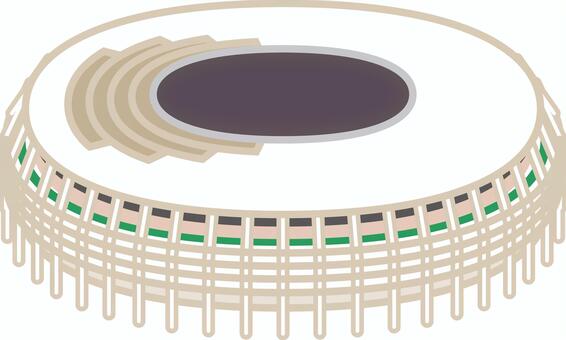
2022年7月24日