


 |
2022年7月10日 日曜日 山形県 | |||||||||||
| 東京駅 | 米沢 |  |
羽黒山(五重塔・三神合祭殿) |  |
酒田(泊) | |||||||
| 8:56発 | 11:04着 | 14:00~15:42 | 18:33着 | |||||||||
JR米沢駅。
米沢牛がいる。

米沢駅前。

長い名のモニュメント、
『活力と創造と愛の21世紀都市・米沢をめざして』。















これから三日間乗るバスに行く。

バスは1号車と2号車に分かれた。
えいちゃんは2号車で、進行方向右側、前から5番目。
理由は忘れたが、「三日間とも席は変わりません」と添乗員さんから説明があった。
![]()
旅行の道路ルートが周回でなく折り返しが多く、席を変えない方が不満が少ないことは後で思った。
逆に言えば、期待していたコースを通ることなく単純でがっかり感もすこしあった。
![]()

1号車と2号車は同じツアーだが、時間が常に10分前後時差があり、
2号車の人と話したり、一緒になる時間はほとんどなかった。

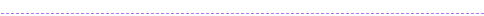
運転手さんもバスガイドさんも三日間同じ人。
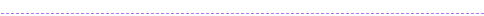
バスガイドさんは女性で、山形なまりが多かったが、聞いていてあの山形弁は演出を含んでいるようにも思った。
(どちらでもいい話だが)
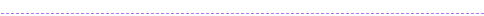
子どもの頃から、バスガイド=美声で歌をうたう、というイメージがしみ込んでいるが今回のガイドさんは一度も歌を披露することはなかった。
東北地方は民謡の宝庫だからガイドさんが歌わなくても、テープでいいから聴いてみかった思いはある。
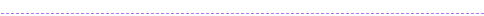

「山形県の歴史」 山川出版 昭和45年発行
出羽国の始まり
諸説あるが、越の国の「出端(いでは)」という意味だろう。
和銅元(708)年、越後国はあらたに出羽の郡を建てることを言上し、朝廷がこれを許可している。
神亀元年(724)頃より、出羽の蝦夷を鎮圧が始まった。現在の秋田県方面の蝦夷経営が本格化した。
最上川舟運
西廻り航路の発達とともに、最上川舟運も一大発展をみた。
幕領、諸藩の年貢米のほとんどが上方へ運ばれた。
輸送路に恵まれない米沢藩は、仙台や新潟など一定していなかったが、巨費を投じて難所黒滝を開削をして、最上川下しとした。
河岸の盛衰
大石田の発展はいちじるしかった。
上り下りの多量の物資は、各荷宿から出入りし、川船の輸送に従事する船頭、水主と呼ぶ労働者がいた。
大名手船と大石田船の対立などがあった。大石田港と上郷の港のとの対立もあった。
大石田船(5人乗り、米375俵)に対して小回りのきく小型舟の登場があった。
奥羽線の開通
米沢に明治32年、新庄に明治36年、秋田県とは明治38年全通した。酒田線は大正3年に開通した。
最上川水運でにぎわった河岸場町のさびれようははなはだしかった。
本合海は、火が消えたようにさびれ
大石田は、船乗り・船大工は人力車夫や荷車引きになったり、移住していった。

「山形県の歴史」 山川出版 昭和45年発行
出稼ぎ
高度経済成長のひずみは、農村地帯にひどい。
新庄市・最上郡など最北地域は「米作と製炭」の、半自給的な生活をしていた。
製炭が急激に衰え、低所得では生活を維持できなくなった。
高度経済成長による労働者の需要拡大が、潜在的失業の農家労働力に手を伸ばした。
最上の「出稼ぎ農家」は、昭和39年で農家の34%で、実際は更に多い。
![]()
月山に雪が見えてきた。
三日間の天気予報はよくなかった。初日・二日目が曇り、三日目が雨。
この晴れの空と、月山の雪は、これから始まる旅行に、おおいにテンションをあげてくれた。

田舎にぽん、超高層マンションが建っていた。
上山市の「スカイタワー41で、地上41階、高さ134mで東北地方一の高層ビル。

最初販売価格が高すぎて売れなかったが、
大幅な値下げを連発、ついに完売したそうだ。
山形県の県都・山形市。

月山はどんどん近く、そして大きくなってきた。

東北中央自動車道の山形ジャンクション。
ここで左折し、酒田方面(山形道)へ向かう。

![]()
最上川をわたる。
最上川
「日本の城下町2東北(二)」 1981年3月ぎょうせい発行
山形市の築城と城下町づくりは最上義光によって行われた。
義光は最上川の三難所を削岩させ船便をひらいた。
山形を玄関として、幕府天領米・藩米は最上川を下って酒田から海路・江戸に送られ、
西回り航路がひらけると最上産の紅花・青そなどが京都・大坂・奈良へとおくられるようになる。
返り荷には、塩・砂糖をはじめ瀬戸物・太物・古手物・操綿・木綿などが送られてきた。
最上川水運がととのったのは寛文(1596~1673)にかけてである。
京都や奈良へ紅花・青その交易に先鞭をつけたは近江商人で、日野系と八幡系。
紅花は陽暦でいえば7月はじめから咲きだし、15日間くらいで終わる。
農家が朝早く摘んだ生花を、サンベと呼ばれる買人が買い集めて、山形の花市に持っていって加工する。
享保の頃、京都の花問屋が生産地で直接買い取りをはじめた。
そのころ、生産者農家も、自分の庭で花餅をつくるものが増えてきた。
明治初年、化学染料が輸入され出した。

![]()
寒河江サービスエリアに着いた。


![]()
まゆはきを 俤(おもかげ)にして 紅粉(べに)の花 芭蕉
![]()
山形県・紅花

![]()
「紅花(べにばな) ものとの人間の文化史」 竹内純子著 2004年 法政大学出版
江戸初期から栽培された最上山形の紅花は、色素が豊富で特に京都西陣の染織物に勧化され、衣類の華美となった元禄のころから需要を増し、
輸出量は「最上千駄」といわれ、豊年のときは千三百駄にのぼったといわれる。
これらの積荷は最上川は舟で下り、酒田港で大船に積み替え、敦賀に入り、京都や大坂に輸送された。
紅花は花も葉も薊(あざみ)に似る越年草で、秋に種を蒔き、7月に花を咲かせる。
花は枝の末(先端)から咲き始め、その花弁を摘むので「末摘花」という異名が生まれた。
紅花は染料と顔料の二つの面を持つ、これは植物のなかでは紅花と藍だけである。
染料を得るため「寝かせ」という発酵の過程があり、熱を嫌うという共通点がある。
藍と紅花は相違点がありながら、その後は明暗を分けた。
藍は木綿と相性がよいことから仕事着から普段着まで用いられたが、紅染は絹に染めつくため庶民の普段着用にならなかったのである。
紅花は葉や茎を乾燥して煎じ、民間薬として飲用され、間引きした紅花は茹でて食用にしていた。
種は油料である。
栽培の人たちは「紅花は捨てるとこがない」といわれていた。
芭蕉は奥の細道のどこで紅花を見たのか
尾花沢では紅花栽培はほとんど行われなかった。
芭蕉は尾花沢で10日間を過ごした。そのうち3日は清風宅で、あとの7日は養泉寺だった。
この間、雨の日が多かった。
芭蕉は尾花沢から立石寺に向かうのだが、楯岡村までは清風が用意してくれた馬で行った。
山形領に立石寺という山寺あり。慈覚大師の開祖にて、殊に清閑の地なり。
一見すべきよし、人々のすすむるによりて、尾花沢よりとってかへし、その間七里ばかりなり。
芭蕉が紅花を見たのは、尾花沢から立石寺に向かう道中であろう。
![]()
「山形県の歴史」 昭和45年山川出版社発行
涼しさを 我宿にして ねまる也
松尾芭蕉が尾花沢で、”紅花大尽”の清風にもてなしを受けた際の気持ちが句によく出ている。
最上地方の名産「紅花」はなぜ衰退したのだろう?
養蚕・生糸業の発展
”最上紅花”として全国に名をはくした村山地方の紅花が衰退したのは、
幕末に支那紅が輸入され、さらに明治にはいり、廉価な新紅と呼ばれた化学染料”洋粉アニリン”が、大量に京都に輸入されるようになってからである。
河北町の明治3年の記録に「畑方は紅花もよろしからず。百姓一同大いに困りいりそうろう」とある。
明治3年の山形県の産額は1万2千貫目、その翌年は半分、やがて統計書から姿を消した。
いっぽう製糸・絹織物は飛躍的な発展をみた。
![]()
「山形県の歴史」 山川出版 昭和45年発行
最上紅花の発展
紅花は、相模・出羽・上総・筑後・薩摩が産地だが最上山形がもっとも良質とされた。
最上紅花が全国の約半分を占めていた。
紅花は豊凶の差がはなはだしく、日照りや花どきに多雨があると半作にも達しない。
農民にとって貨幣収益がよく、換金作物だった。
紅花作には金肥が必要であり、摘み取り期の労働力の制約があり、規模拡大には限界があった。
農民が収益をあげられるのは、農民みずから干花加工を行った場合である。
花摘みから花餅まで一ヶ月、女・男・子供・賃労働者で行った。
紅花商人
前期の商人で代表は、紅花大尽といわれた尾花沢の鈴木清風であろう。
芭蕉の「奥の細道」でも紹介されている。
後期に栄えた紅花商人の多くは、現在の金融・商業界の中心的存在といってもいい。
全国にその名をはくした“最上紅花”は、幕末に支邦紅が輸入され、明治に入り化学染料が輸入され、衰退していった・・・・
商業・金融・木綿・絹・瀬戸物・書籍まで多様な営業内容で、質流れ旧地を獲得する形で、土地集積は進んだ。
![]()
6月7月はサクランボの季節。
サトウニシキ、1箱600円。

![]()
芋煮会
東北といえば・・・・芋煮会。
山形といえば・・・芋煮会の本場。

あっ寒河江サービスエリアのメニューに「山形いもに」がある!
(芋煮会は秋のイメージだったので、自分にとって予想外の発見だった)
即注文!!!

これが「いも煮」です。
芋煮は一人でなく、仲間や家族や職場の人たちで食べるもの。それで、いつも「芋煮会」になるが、今日は特別。

やっぱり”芋煮”はええなあ。
腹は減ってなかったが、美味かった。

![]()
![]() 羽黒山①五重塔
羽黒山①五重塔 ②
②
クラブツーリズム 『出羽三山と秘境・鳥海の絶景3日間』
2022年7月21日
![]()