
 |
2022年11月25日 金曜日 | 府中 | 新市 | 神辺・千田 | ||||||||
| 福山市新市町新市 | 9:01〜10:39 | 10:58〜12:24 | 13:08〜13:37 | |||||||||
| 「しんいち歴史民俗博物館」 | ||||||||||||
ここは「福山市役所新市支所」。

新市小学校は、校内マラソン大会。

大佐山を向いて少し歩けば「しんいち歴史博物館」がある。


”新市”といえば”備後絣”の地元。
その基を築いたのが「富田久三郎」翁。

博物館のリーフレットには次のように記されている。
![]()
備後絣
備後絣は1853年(嘉永6)、備後国芦田郡下有地村の富田久三郎(1828〜1911)が、
備後地方で初めて絣の技術を創案し、その製法を近郷の農家の人々に伝えたのが始まりです。
1861年(文久元)には商品化され、1868年(明治元)に「備後絣」と名を改めて大阪へ出荷されました。
当時の備後地方では、農業の他に大きな産業がなく、多くの農家が副業として取り組み、絣織りは広まってゆきました。
そのうち農家から織物に関する仕事を専業にする者も現われ、地域の産業として多くの人が関わるようになりました。
その後、
染料や紡績の進歩、製造工程の分業化と機械化により絣は大量に生産されるようになり、福山地域の主要産業へと発展していきます。
備後絣は全国各地に出荷されましたが、その後の生活環境の変化や化学繊維、化学染料の進出に押され、生産は徐々に減少に転じます。
絣を作り出す優れた織物の技術は現在でも活用されています。
![]()
高機(たかはた)は、父の話では、家に使われなくなったものが、まだあったそうだ。

明治時代の中頃までは、備後・備中・備前や瀬戸内地方では、
(塩田を除き)
五穀と芋と野菜と綿を作り、
それを食べ、
それを着ていた。
綿花を栽培し、糸を紡ぎ、布を織り、着物に仕立てる。
根気がいる作業だが近年まで、どこの家庭でもそうしていた。


![]()
なお、 「しんいち歴史民俗博物館」には驚くほど多くの、古代〜近世の出土品が展示されている。
さらに説明も充実していて、予想を越えた博物館だった。
![]()
![]()
![]() 素戔嗚神社
素戔嗚神社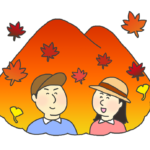
2022年11月29日