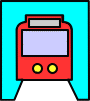
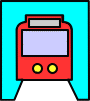
| 2021年12月25日 土曜日 愛媛県松山市丸之内 松山城 | ||||||||||||
| 松山城 | 堀端 | 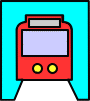 |
道後温泉 | 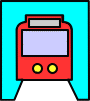 |
松山 | 岡山 | 笠岡 | |||||
| 7:30頃 | 10:00頃 | 10:25~11:45 | 12:09・12:21 | 15:11・15:23 | 16:07 | |||||||
これから朝の散歩に出る。
午前6時51分、二番町の「松山ニューグランドホテル」。

朝の松山大街道。

「大街道交差点」。
松山城ロープウェイ乗り場の前を行く。左に「坊ちゃん」の像が見える。

「東雲口登城口道」より登城を始める。

道には灯りがともっていた(下山時には消えていた)。

番町・千舟町方面を望む。

ロープウェイの乗り場と合流する。

”荒城の月”。(櫓の屋根の上)

「春や昔15万石の城下かな」と俳人正岡子規が詠んだ松山市は、
瀬戸内海に面した気候温暖、美しい風光に恵まれた土地で、愛媛県の中心地であり、四国第一の都市である。
この地に城を築いたのは、賤ケ岳七本槍の一人として活躍した加藤喜明である。
築城と同時に城下町も整備された。
それが現在の松山市街地の基礎になった。
喜明は1627年会津へ転封され、蒲生忠知が入部。在城7年で没し、伊勢国桑名城主松平定行が15万石で入部。
以来、松山は松平家15万石の城下町として栄え、明治維新を迎えた。
「日本の城下町10四国」 ぎょうせい 1981年発行

「戸無門」は、
門扉がない。

筒井門。

太鼓門。

松山城
昭和30年代以降多くの櫓や門を木造で復元してきており、本丸部分はほとんど旧状に復しているので、往時の城の姿を知ることができる。
平山城の現存天守としては最も高い標高に聳える。
まさに松山のシンボルである。
「城と城下町」 西日本城郭研究会 メイツ出版社 2011年発行
本丸広場。



「日本史名城の謎」
桜井成広著 図書印刷 平成1年発行
天守は天明4年(1784)に雷火で焼け、現在のは幕末安政元年(1858)に竣工したものであり、
中に床の間のある畳敷きお書院が設けられているのは古風で珍しく、安土城や聚楽第の天守や、犬山城、岡山城の古式天守にもその例を見る。
本丸の石垣を運ぶのに、魚売り女たちは魚を運ぶ桶に石を入れて登ったというので、
これを賞した喜明はその桶に「御用櫃」という文字を書かせ、以後税を免除したという。

南隅櫓、十間廊下、北隅櫓
北隅櫓(左)は小天守北ノ櫓とも呼ばれ、大天守に次ぐ格式を持つ。
十間廊下が北隅櫓と南隅櫓を連結する。
「城と城下町」 西日本城郭研究会 メイツ出版社 2011年発行

松平家の四代藩主貞直は俳諧をたしなみ、その影響もあってか領内では俳諧が盛んになった。
この土壌から子規や高浜虚子を輩出し現代俳句へと発展した。
「城と城下町」 西日本城郭研究会 メイツ出版社 2011年発行


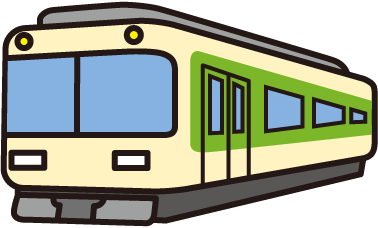

![]()
![]() 松山城②
松山城②
「JR西日本・四国くるりきっぷ」 (2021.12.25)
2021年12月29日