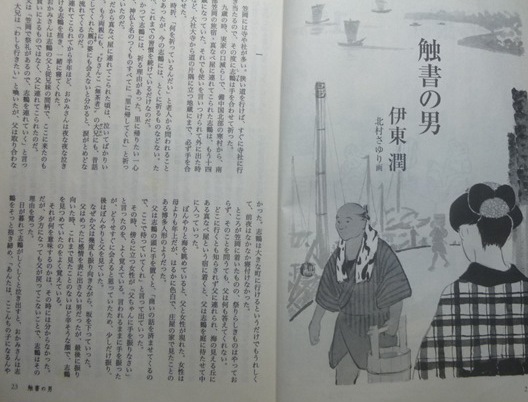| 2017年12月28日 木曜日 |
|
12:51〜14:31 |
|
|
| 笠岡市笠岡 |
|
|
|
| 〜潮待ちの宿・触書の男〜を歩く |
|

おかみさんから仰せつかった品物を、大仙院から続くおかげ街道沿いの商家に届けた帰途、志鶴は番屋のある広小路に回ってみた。
大仙院。


大仙院の前。

煙草盆を引き寄せると、佐吉は細刻みを詰め始めた。
「倉敷を通って来たお客さんが、こんなものを持ってきたんです」
志鶴が触書を渡す。
「いかにも、この絵は似てるよな」
佐吉が似顔絵をしげしげと見つめる。
番屋があった広小路。

番屋から少し離れて陣屋、貫閲講堂周辺。


「ここに落ち合う場所が書いてある」
佐吉が指し示したのは笠岡北端の北八幡宮である。
「ここで一味と待ち合わせし、夜陰に紛れて港まで押し出し、亀川屋の蔵を襲うつもりだったんだろう」
見晴らしのいい北八幡。

応神山や龍谷高校。

古城山。

北八幡参道。
びっくりしたのが”南無八幡大菩薩”の幡。

明治の初め、
八幡さんと菩薩は、神と仏で分離された。

客の与三郎は、亀川屋の蔵が立ち並ぶあたりに来ると、何かを探るように念入りに歩き回っていた。

亀川屋は笠岡港の蔵元で、廻船業を営むだけでなく、備中西部の天領から津出しされる廻米の収納業務を請け負っていた。
胡屋とは競合関係にあり、天保の頃までは、双方が共に収納業務を行っていた。
胡屋は幕府の通達を破る不始末を仕出かしたので、廻米業務は亀川屋が独占するようになった。

亀川屋は元笠岡郵便局を中心に、海に面して広大な蔵屋敷だった。

江戸時代の古図にはお寺と並び亀川屋の屋敷が載っているが、
今は想像するだけ。
江戸末期か明治の初めに没落したようだ。


「それでは笠神社にお礼を言いに行ってきてもいいですか」
「いいわよ。行ってらっしゃい」
志鶴は笠神社に至る石段を上った。

なぜか胸が高鳴る。
笠神社に着いた。
清冽な空気が胸いっぱいに満ちる。
漁船が沖に向かって漕ぎ出していく。
------今日も大漁で、無事に戻ってこられますように。漁船の無事を祈ることで、自分も幸せになれるような気がする。
------わたしは、この町で生きていく。
志鶴は拝殿に近づいていった。(了)

雑誌・オール読物に連載中の「潮待ちの宿」は2017年12月号で第三作目迎え船が掲載されている。
第一作・触書の男
第二作・追跡者
第三作・迎え船
第一作は巻頭の写真頁の次、最初の作品として掲載された。
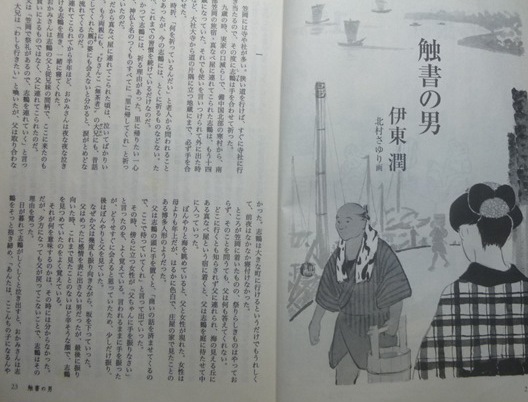

 つぎ・2017「物故者」
つぎ・2017「物故者」
2017年12月30日